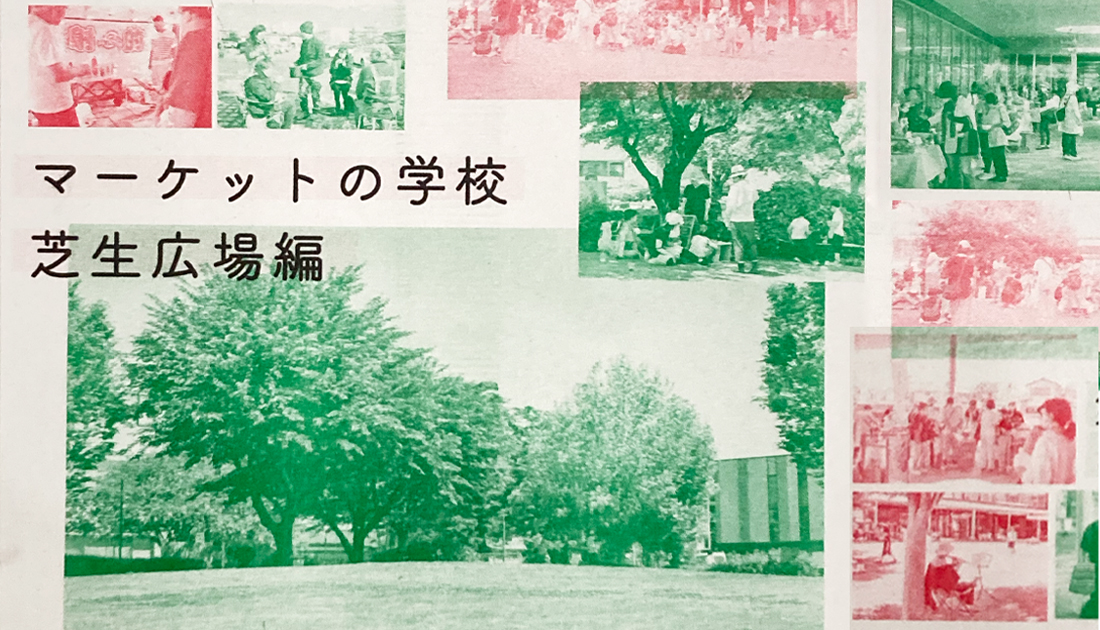マーケットの学校について
マーケットの学校は、2020年9月にスタートした市民参加型のワークショップです。マーケットとは、仮設のお店が集まり日用品や食べ物の売買が行われる、誰でもふらっと立ち寄ることができる場のこと。北本では、奇数月に市役所芝生広場で「&green market」が、偶数月には北本団地商店街で「団地マーケット」などが開催されています。飲食物や物販の販売だけでなく、弾き語りや作品の展示、こどもが店主になるこどもマーケットも開催されるなど、やってみたい気持ちの背中を押す場としても機能しています。
マーケットの学校は、市役所芝生広場で開催している「&green market」を実践の場とし、対話と実践を往還することで、北本でのマーケットの在り方や暮らしの楽しみ方について考えていく連続プログラムです。
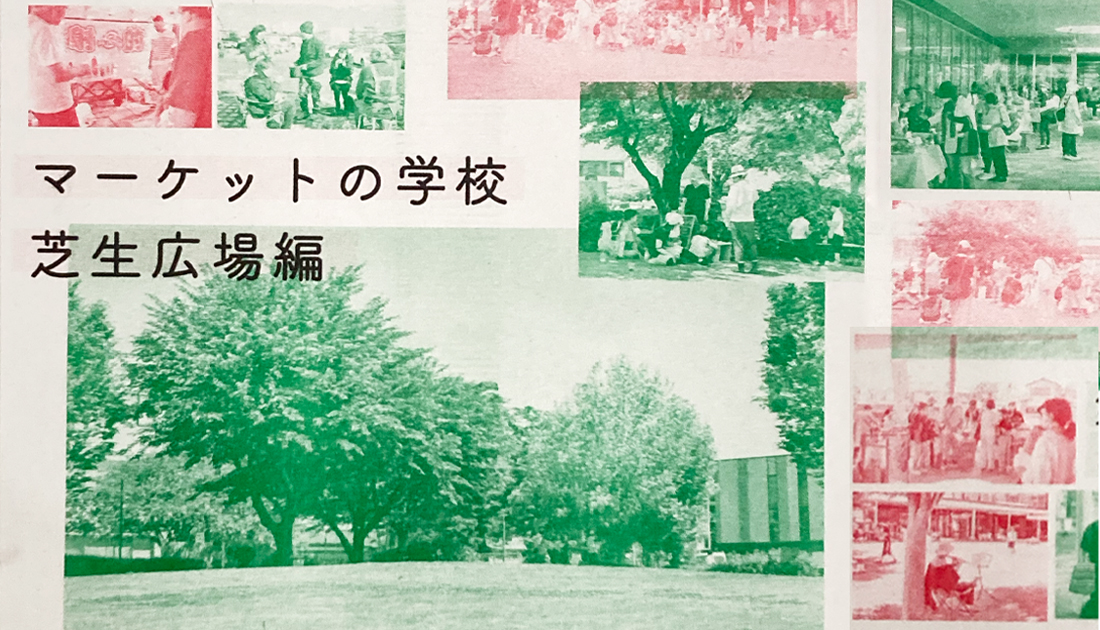
きたもとで考えるマーケットの学校 芝生広場編
北本市役所の芝生広場で定期開催される「&green market」は、市内や近隣から様々な人が集まり出店者もお客さんも一緒になって思い思いに楽しむことができる、北本暮らしの魅力がギュッと詰まったマーケットです。また、最近では芝生広場を会場に、提案者と市が共催してマーケットを開催する連携事業も行われています。(リンク:市役所みどりの広場を活用したマーケットの共催)
様々なマーケットが開催される北本市役所芝生広場ですが、あくまで庁舎敷地の一部であり、公民館の様な貸館利用はできません。2024年度のマーケットの学校では、公園のような場でありながら、定期的にマーケットが開催されている『北本市役所芝生広場』を舞台に、改めて『公共の場』ということについて皆で考えていきます。

公共の場について考える
2024年8月31日に開催された第1回ワークショップに続き、2024年10月19日に第2回ワークショップが北本市役所会議室を会場に開催されました。各回ごとに参加するメンバーと一緒に、雑談形式で話をしながら、様々なトピックを話し合うのが『マーケットの学校』です。
第2回ワークショップでは、市内外の農家さんやいつもマーケットを手伝って下さる方、マーケットを自身で主催されている方、市役所職員や事務局など、9名の参加者で講座がスタートしました。冒頭の自己紹介も終わり、まずは前回の振り返りから講座に入っていきます。2024年8月31日に開催された第1回目の講座では、主に参加者が芝生広場でやりたいことを皆で話し合いました。&green marketを運営し講座をコーディネートする合同会社暮らしの編集室の江澤さんから、前回のワークショップで出てきたアイデアを皆さんに共有します。「子どもとお年寄りが楽しめるマーケットをつくりたい」「紙飛行機大会や昭和の遊びを地域のお年寄りが子供に教えるコーナーがあるといい」「読み聞かせや料理スペースを設けて、マーケットが出会いの場としても機能したらいいのでは」第1回目の講座では芝生広場を舞台とした様々なアイデアが参加者からよせられました。

マーケットの学校へ参加者されている皆さんの多くは、&green marketへの出店や参加がきっかけで講座に参加されているとのこと。そこで、きっかけとなった&green marketについて、印象に残っていることを話し合ってみようと話題は移ります。ここでは皆さんから出された意見について少しご紹介します。
・軽トラで出店していた農家さんが家で採れた柚子をくれたのが嬉しかった。
・ごちゃまぜでテーマみたいなものがない。
・大豆から作るきな粉づくりワークショップでは、子どもの常連さんがついたのが嬉しかった。でも初めてやったときは袋のビニールが熱で溶けたりと大変だった。
・ここに来ると仕事じゃないけれど役割がある。
・居場所でもあり小さなチャレンジもできる。トライ&エラーができる。
・家にあるものを持ち寄る雰囲気。
・出店していてもなんだか居心地がいい。
皆さんの話からは、&green marketで起こっている具体的な事柄に加え、会話の端々に『雰囲気』や『居心地』というキーワードが多くでてきます。参加しているメンバーの多くは、&green marketの雰囲気が印象として残っており、その雰囲気が自分にとってもお客さんにとっても居心地のよさにつながっているということが、話し合いを通して見えてきました。「では、講座の後半ではこの“居心地”について話してみましょうか」と、江澤さんから講座後半のテーマが投げかけられます。

休憩をはさみ後半の講座がスタートします。さて、&green marketに漂っている雰囲気や居心地とは何なのでしょうか。少し考えた後、メンバー皆さんからは様々な意見が出てきます。マーケットに出店している女性からは「一回限りではなく続いていくことに安心感がある。あとは出店場所も決まっていないのが最初驚いた。そういうことが関係しているかも」と、マーケットが継続開催である安心感や、自由な雰囲気が居心地に関係しているのではと話します。お手伝いで参加している男性からは「あまり企まないというか、いい感じでちゃんとしてない。あとなにか役割があることが重要なのでは」と意見が出てきます。他の女性からも「顔の見える関係が居心地のよさを生むのでは」と、出店者同士も含めたその関係性について意見が出されました。「やっぱりラボというか焚き火の存在が大きいんじゃないかな」「そうだね、それは大きいかも」色々な意見の中でも“焚き火”という話が盛り上がってきました。
&green marketでは、ほぼ毎回のように“焚き火”が行われています。火を囲みながら、冬は暖を取り湯を沸かし、子どもや大人もマシュマロやネギ・サツマイモなどを焼き、食べたりおしゃべりをしています。マーケットではこの焚き火ブースのことを、色々な試行錯誤を楽しむ場として通称“ラボブース”と呼んでいます。

薪割りなども体験できるため、一見すると子供が多い印象がありますが、実はそうではないと毎回ブースをお手伝いしている男性は話します。「もちろん子供も多いけど、実は大人の男の人がただ焚き火にあたりながら座っているという事も結構ある。しゃべったりしないから目立たないかもしれないけれど(笑)食べたりおしゃべりしなくても、なんかくつろいでくれているのはいいよね」すると一緒にラボブースを手伝う女性からこんな意見が出てきました。「わかります。でも私はそういう時、この人実は話しかけてほしいのかな。でもどうしようかなって一人で勝手に迷っちゃうんです」と、その時の心情を教えてくれました。

ラボブースでは火を扱うこともあり、必ず運営スタッフがお客さんの様子をそっと見守っています。火の状態はどうかな。薪割りは安全にできるかな。といった様子です。もちろん自分自身も野菜を焼いたり、賄いを食べながら。見守りというほどの大げさなものではないかもしれませんが、その方がいることで、場に安心感というかお客さんとの自然な交流が生まれていきます。
しかし、皆さんに分け隔てなく気さくに話しかけいる様に見えるが、実はお客さんへの声がけや気配りが、ケースバイケースで難しいという話は“居心地”という事を考えてみるうえで、とても重要なポイントだと感じます。
おしゃべりしたくて来る人もいるし、ゆったり静かに過ごしたい人もいる。家で一人で過ごすのではなく、誰かのとなりで時間を過ごしたいと思いマーケットに来る人もいるかもしれない。「何を心地よいと思うかは人それぞれ違うけれど、出来るだけその人なりの心地よさを大事にしたいよね」そんな気持ちが皆さんの話し合いからは伝わってきます。


“関わりしろ”の余白を残して
今回の講座では第1回目講座の振り返り、&green marketを例に“居心地ってなんだろう”という話題について、皆さんで考えてきました。「&green marketは、積極的にこういう場にしたい。こういうお店だけを呼びたいと思って運営はしていないんです。どちらかというと、市役所前にこんなに気持ちのいい芝生広場があるから、一緒にどう?という感じです。場を開くこと以外はあまり手を入れないで、そこに集う人がそれぞれ考えながら、話しながら一緒にできたらと思っています」運営の一人である江澤さんは話します。

誰かと関わらなくちゃ。何かをしなくちゃ。と身構えるのではなく、関わりしろの余白を持ちながらゆったり同じ時間を過ごしていく。&green marketから考える“居心地”ということについて、なんとなくこんな輪郭が浮かび上がってきました。それは、何かと個人の意欲や自発に基づく積極性と計画性が求められる社会の中で、例えば「何かあったら言って下さいね」という様な、受動的だけどあなたのことを気にかけていますという各々の態度や姿勢が、&green marketの空気をつくっているのかもしれません。