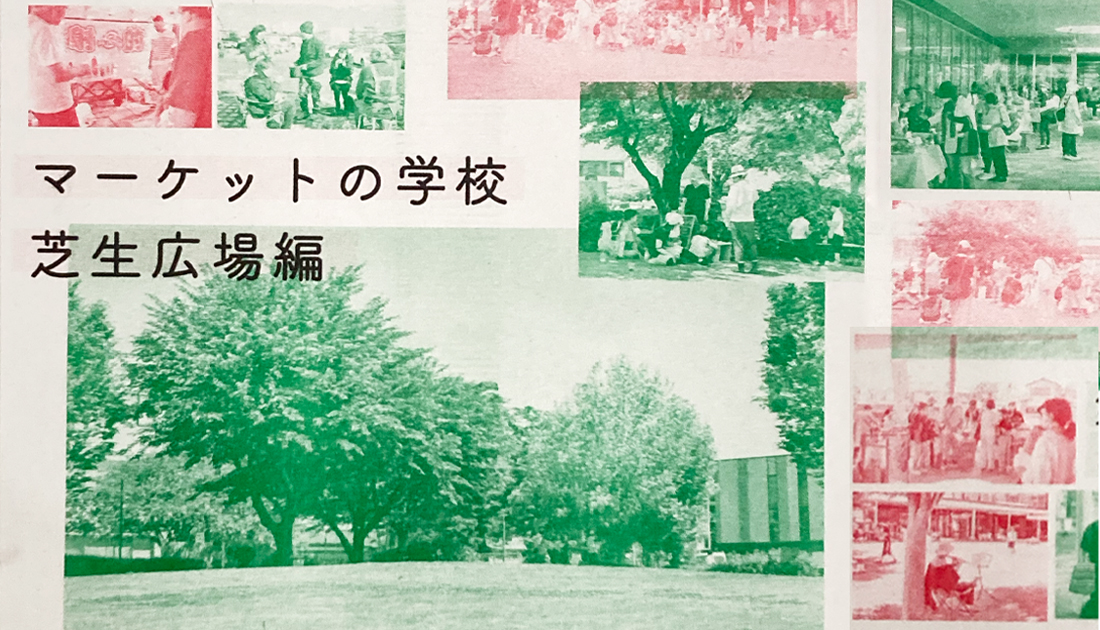マーケットの学校について
マーケットの学校は、2020年9月にスタートした市民参加型のワークショップです。
ここでいうマーケットとは、仮設のお店が集まり日用品や食べ物の売買が行われる、誰でもふらっと立ち寄ることができる場のこと。北本では、奇数月に市役所芝生広場で「&green market」が、偶数月には北本団地商店街で「団地マーケット」などが開催されています。飲食物や物販の販売だけでなく、音楽や作品の展示、こどもが店主になるこどもマーケットも開催されるなど、やってみたい気持ちの背中を押す場としても機能しています。
マーケットの学校では、主に市役所芝生広場で開催している「&green market」を実践の場とし、北本におけるマーケットの在り方や暮らしの楽しみ方について考え話し合っています。マーケットの多様な可能性を考えながら対話と実践を行ったり来たりすることで、まちや場所、地域や関係性に対する理解を深めていく連続プログラムです。
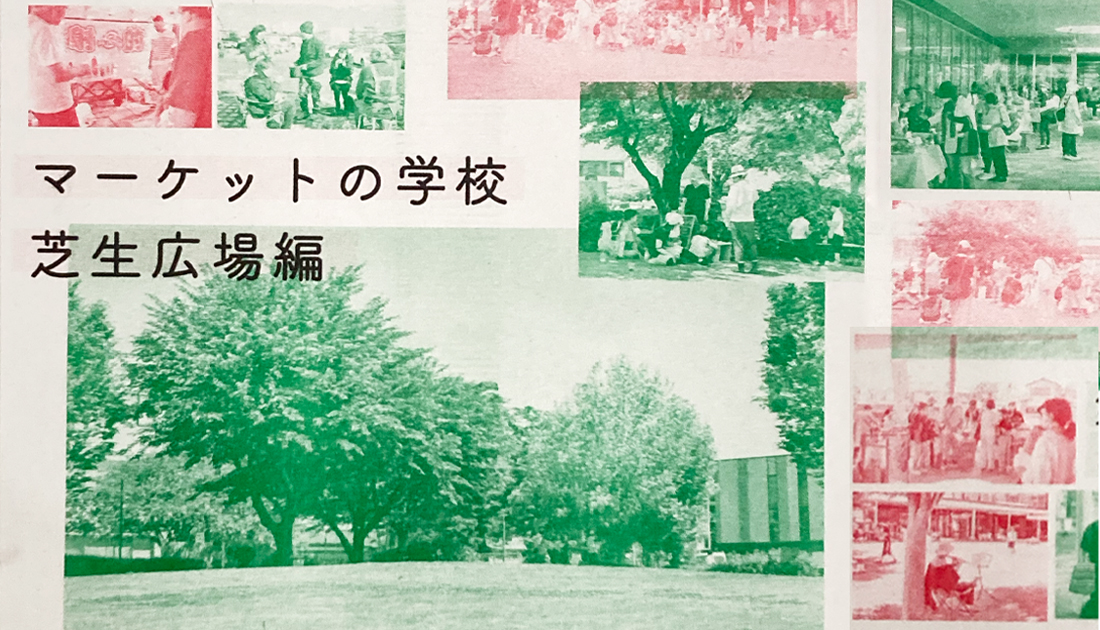
きたもとで考えるマーケットの学校 芝生広場編
北本市役所の芝生広場で定期開催される「&green market」は、市内や近隣から様々な人が集まり出店者もお客さんも一緒になって思い思いに楽しむことができる、北本暮らしの魅力がギュッと詰まったマーケットです。また、最近では芝生広場を会場に、提案者と市が共催してマーケットを開催する連携事業も行われています。(リンク:市役所みどりの広場を活用したマーケットの共催)
様々なマーケットが開催される北本市役所芝生広場ですが、この場所はあくまで庁舎敷地の一部であり、公民館の様な貸館利用はできません。2024年度のマーケットの学校では、庁舎敷地でありながら公園のように活用されたり定期的にマーケットが開催されている『北本市役所芝生広場』を舞台に、改めて『公共の場』について皆で考えます。

公共の場について考える
2024年度は「公共の場について考える」を軸に話し合いを続けてきました。各回ごとに参加するメンバーと一緒に、雑談形式で話をしながら、様々なトピックを話し合うのが『マーケットの学校』です。このレポートでは2025年2月22日に行われたマーケットの学校 第4回ワークショップの様子を振り返ります。
ステイトメントから考える
この日は2020年のマーケットの学校の時に定めたステイトメントを軸に話が始まりました。ステイトメントという言葉自体があまり馴染みのないものかもしれませんが、日本語に訳すと声明、声のような意味を持っています。ルールや約束事よりは曖昧だけど、迷った時に立ち返ることができる、マーケットの学校やマーケットの現場に置いておきたい言葉として設定されています。参加者の岡村さんは「最初はふわっとした言葉だなあと感じていたけれど、継続して参加していく中でその曖昧が色んな解釈の余地をもたらしていて、納得することが多くなった。」と話します。確かに具体的なことはあまり話されておらず、行動の指標や心持ちを表すような言葉が多いです。

当初から参加する暮らしの編集室の岡野さんからは「ステイトメントを定めた当時はまだ&green marketも開催していなかったので、こうなったらいいなと理想について話していた気がします、でも最近は&green marketで起こったことをベースに話をすることが多いので、そこは変わってきてる気がする」と意見が出ました。5年間継続してきた中で関わる人も入れ替わったり、お客さんも増えてきています。半面、変わらない、変えたくない部分もあるように思います。北本らしさ、&green marketらしさってどんな所だろう、何を大事にしているんだろう。そんなことを考えながら、新しくステイトメントに加えてみたい言葉を探しました。

マーケットの可能性 雑談
最初に出てきたキーワードは「雑談」。実際にマーケットに出店している福田さんからは「鳥好きのお客さんがいて、いつも作品を見にきてくれるんです。その人の飼っている鳥の写真を見せてもらうこともあります。そうやって仲良くなると、今度はその人に向けて作品を作ろうって準備したりもするんです」というお話が。継続して出店していく中で売買からはみ出していくような会話=雑談が生まれると、出店者とお客さんという従来の関係を超えたコミュニケーションが生まれます。お客さんに合わせてオーダーメイドのように作品を作る福田さんはある意味、お店というより仕立て屋さんのような役割になっているし、いつも鳥の話をする友人のような関係であるともいえます。福田さん自身も、出店を通して関係が生まれることを楽しんでいるそうです。
また別の参加者さんから「普段街中では知らない人に話しかけるハードルを感じることが多いが、マーケットでは芝生で遊んでいる子供達にも気軽に声をかけられる。出店している農家さんとも野菜の生育状況の話をしたり、会話することも楽しみの一つになっている」と意見が出ました。マーケットの中では人に話しかけやすい雰囲気が生まれているようです。
用があるから話をしにいく市役所の窓口のような場所であったり、会議のように議題に沿って話が進んでいく場では、本筋を逸れてはみ出していく雑談はなかなか生まれません。しかし雑談から生まれていく関係の変化、偶然のつながりやひらめきは、人が生きていく上で実は結構重要なものなのではないでしょうか。様々な理由から雑談が生まれにくくなっている中、マーケットを通して近所に雑談のきっかけが生まれていることは、とても価値のあることなのかもしれません。

出店する側にも喜びや変化がある
福田さんと一緒に子供向けの射的やコリントゲームの出店をしている田口さんは「やってみたいって言ったら保育園の子でも絶対断らないんです。射的も当たるまでやってもらうし、的を倒したら鐘を鳴らしてあげる。楽しい気持ちになってもらいたいから。」と言います。福田さんも「景品のおやつも食べられないからもらえない、とならないように、アレルギー対応のものも用意したりしてます。やっぱり楽しい時間を過ごしてほしいから。」とお話ししてくれました。
出店する側にも売買を超えてやりたいことがあります。お二人は「子供がニコッと笑った顔を見るのが嬉しい、そこから貰うものがある。」とも教えてくれました。
事前にステイトメントの話をしっかりしたわけでもありませんが、お二人の活動はまさにステイトメントの「小さなニーズに確実に応える」を体現しているものともいえます。普段はなかなか出店が忙しく、ここまで話を聞くことが出来ないので、この日、お二人の思いを聞けたことはとても良かったです。企画運営している側としても出店者さんがそういった思いで活動してくれていることは、とても嬉しく思います。

お二人は&green marketへの出店がきっかけで、北本市内の別の地域のお祭りにも出店として呼ばれたそう。最初はとてもアウェーな雰囲気を感じていましたが蓋を開けてみれば多くの子供達が集まって楽しんで、大盛況で終わったそうです。マーケットへの出店やそこでの雑談をきっかけに次の出店が決まったり、つながりが広がっていくことも楽しんでいるようでした。

小さな変化を大切にする こと
ここまで話してきたように&green marketの場には、気軽に人と話す雑談によって偶然のつながりが生まれたり、出店を通して売買以上の実感や喜びを得るなど、集まる人々が、人と関わりながら変化していく面白さがあります。それは一人一人の小さな変化なので数値にしづらく、評価することもまた難しいものかもしれません。しかし継続する中で新しい関係性が育まれていったり、小さな変化を経験する人が増えていくことで、より大きな流れになっていくでしょう。このマーケットが市役所の芝生広場で行われていることも面白いポイントです。マーケットの学校が始まって5年経ちますが、今後10年、20年と続いていくことで市役所のイメージも変わっていくかもしれません。手続きをする場所からマーケットをやっている場所に。窓口の場所から何か面白いことが起こる雑談の場所に。公共の場所のイメージが変わっていくことで、まちのイメージも変わっていきます。そういうまちにはきっと何かやりたい人がたくさん住んでいて、雑談やつながりがたくさん生まれるマーケットが毎週のように開催されているのではないでしょうか。北本がそんな面白いまちに、今よりもっと面白いまちになるように。小さな変化を大切にしながら、マーケットの学校と&green market の活動を継続していきたいと思います。